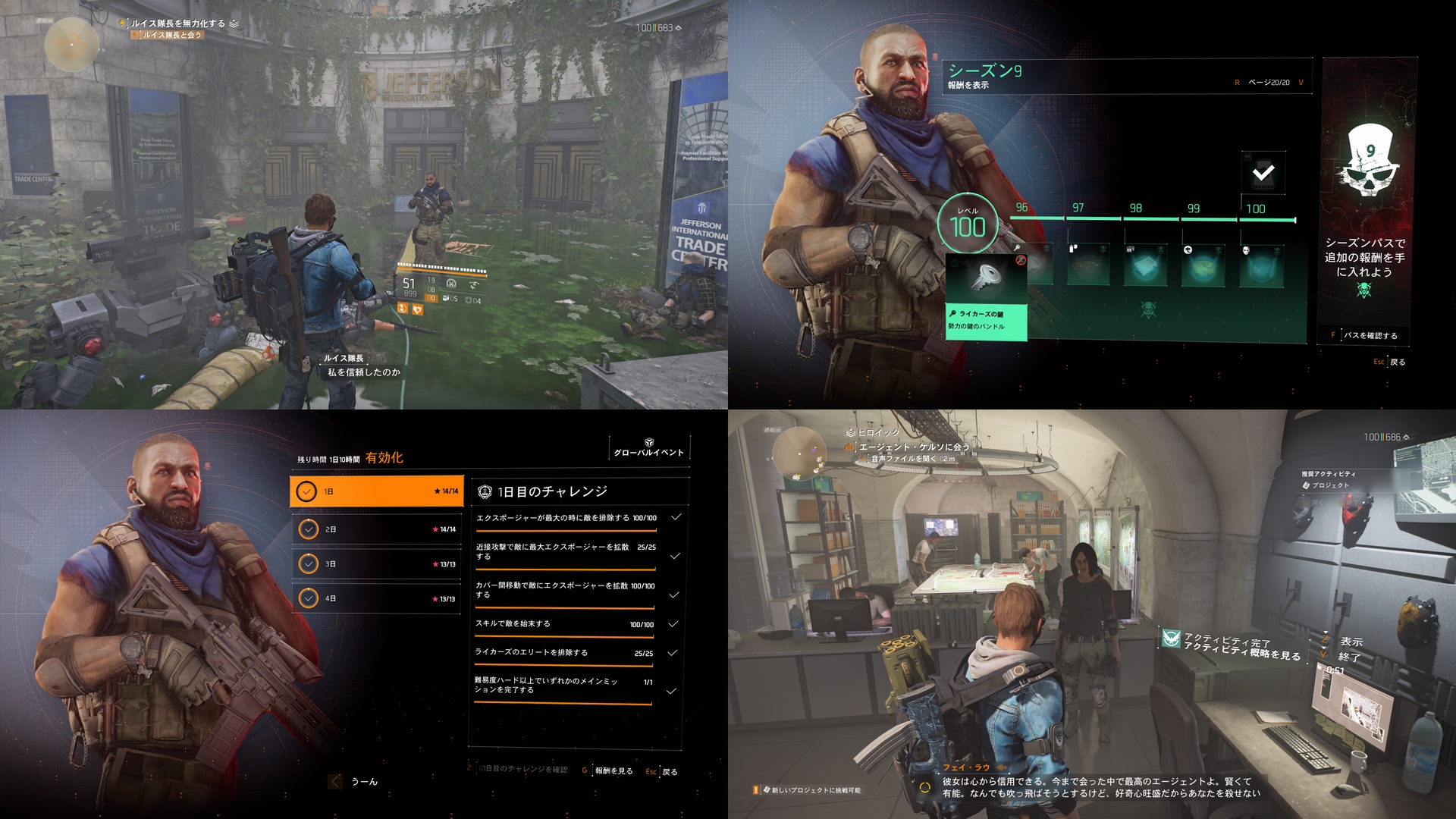続・モンハンライズ・サンブレイク。
盆休み前に、楽しそうな大きめのアップデートが来たおかげで、今年の盆休みは、合間合間に暇な時間ができると、そこでモンハンに興じる生活になった。
今回のアップデートは、何も考えずにただひたすらコツコツと繰り返し狩りまくるという、能天気な楽しみ方がメインのもの(本当か?)だったので、「スキマ時間の埋め草」的な運用にもってこいだったこともあり、非常にモンハンが重宝した。
このアップデートを含めて、サンブレイク以降のモンハンライズはいいね。ゲームとしての立ち位置がわかっているというか、コンテンツの繰り返しプレイの動機付けや、難易度の調整などが、なかなかどうしていい塩梅。
モンハンライズは、ライズ無印の頃はいまいち楽しめなかったのに、サンブレイクになったとたんに楽しめるようになるとは、正直かなり誤算だった。
とはいえ、盆休みにそれなりに長時間プレイしたこともあって、サンブレイクのコンテンツも、だいぶ遊びきった感が出てきてはいる。次のアップデートは9月末くらいなのかな。そこまで持つかというと、それは当然持たないだろうし、一旦プレイをやめた後で戻ってくるかというと、それもまた怪しい。
だから、今後まだどれだけサンブレイクで遊ぶことになるかは、まぁ、付き合い次第かな。
ここからは余談であり、またある意味本題だ。
Switch界では、サンブレイクの次のアップデートまでの間に、スプラトゥーン3という巨大タイトルが来るらしい。
私はシリーズ未経験ということもあり、今のところ本作にさほど興味はないのだけど、ふとPVを観てみたら、ちょっとその内容にはたまげてしまった。オンラインゲームとしての機能の実装っぷりが、充実しすぎていたからだ。
コミュニケーション、コスメといった周辺機能から、プログレッションやロビー機能、マッチング待ちのできる射撃場まで、およそ欲しくなりそうなものが、全部盛りといった様相だった。
この万能感は、PCゲームだとかつてはBrizzardが、昨今はRiotが備えていたものだけど、さすがは任天堂。これらPCゲーム界の雄にしっかり比肩している、いや、むしろ凌いでさえいるな。
日本人としては誇らしいし、PCゲーマーとしてはちょっと悔しい気持ちだ。