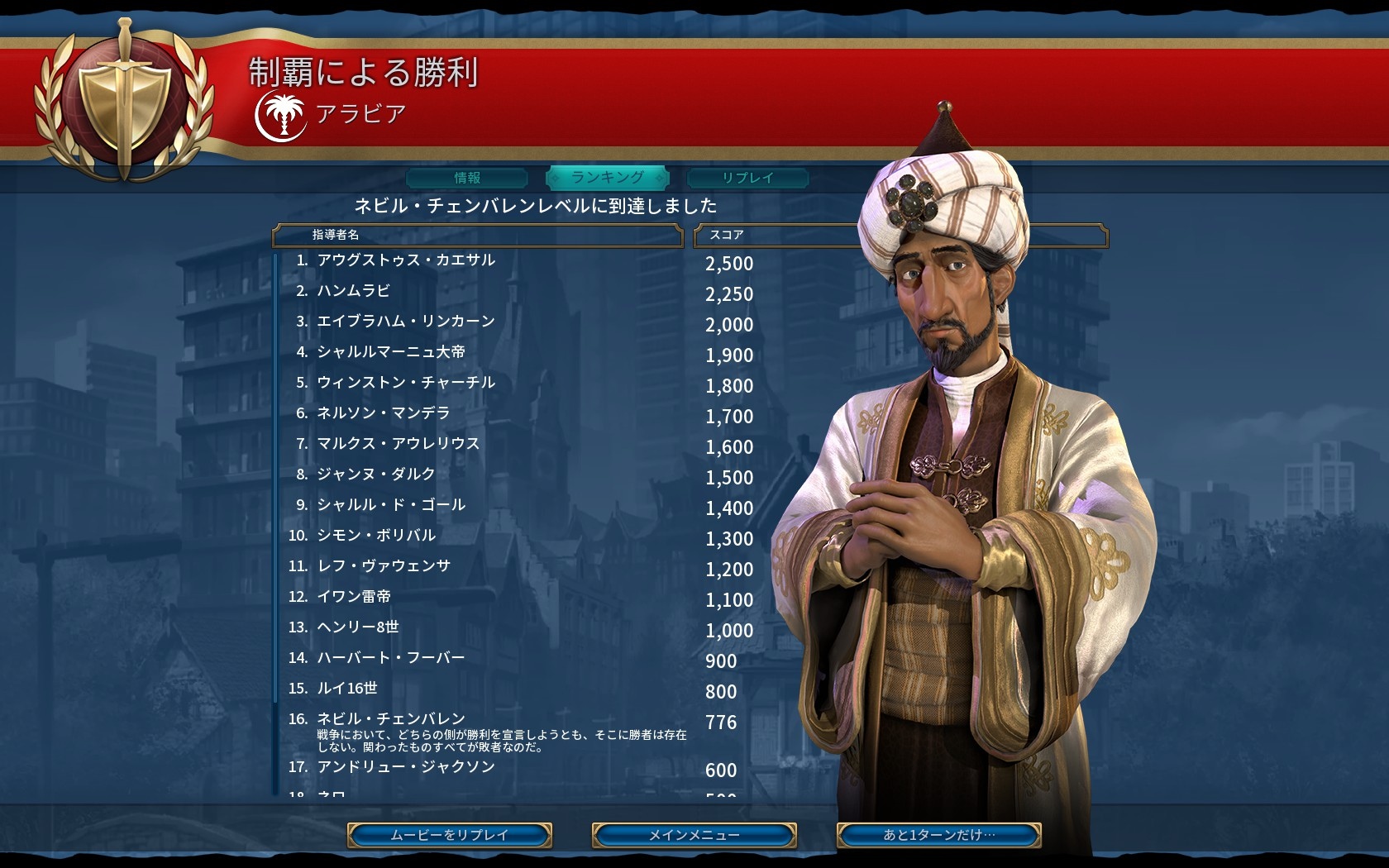Twitterで聞き知ったレースゲームのiRacingというのが、なかなかすごいと感心してしまった。いや、そんなもんじゃないな。
ガツンとやられた、と言っていい。
Steamのレビューを読んだだけで、実際に遊んでいるわけではないから、すべてが正確かどうかはわからないけど、私の理解の範囲では以下のような要素を持ったレースゲームらしい。
- 会費制
- 実名制
- ランク制
- 成績による月間報酬(リアルマネー)あり
うーん、実車によるランキング争いレースを、バーチャルで完全に再現しようという意気込みを、これでもかと感じる。ツールが実際の車ではなく、PCとソフトウェアとハンコンとであるというだけで、やっていることは実際のレース大会そのものだ。悪く言っても草レース大会そのものだ。ゲーム、と呼ぶのがためらわれてしまう。
実名制、というのがひとつのキーのように思える。これで一気に、「ゲームで遊ぶ」感覚から「道具がゲームである競技」という感覚になる。よく揶揄される「遊びじゃねえんだ真面目にやれ」が現実になる。よくも実名制に踏み切ったな、と感嘆するしかない。この辺はFacebookのような実名制のSNSが先行して存在したことが、成功に一役買ったのだろう。
そして集めた会費から、成績上位者への報酬というバックがあるというのも面白い。単純にして明快なモチベーションコントロールだ。
これこそが未来のe-Sportだよな、という気さえする。
ここまでやられると、私個人としてはレースへの情熱が足りないため、逆に怖気づいてしまって、まったくもって参加する気は起きないんだけど、でも、カーレースが好きで、憧れてて、でも実車でレースができるような恵まれた境遇ではなくて、だからそれを体験したくてゲームで我慢している、という種類の人にとっては、このゲームが天恵であることは容易に想像できる。
願わくば自分の好きなジャンルのゲームで、こういうものがあればいいのになぁ、とうらやましく思える限りだ。
今この時代が、e-Sportsというジャンルの勃興期である、という点については異論のないことだと思う。いろいろなゲームで、それをe-Sports化していく取り組みが行われていて、一部のタイトルでは商業的に成功している。
でもその成功の大半は、運営側の努力というか、バーチャルの外の「リアル」な活動による、大規模なプロモーションによるもので、バーチャル内で競技と個人と報酬とが、シームレスに連結されている例は少ない。
大胆に言ってしまえば、e-Sportsというものは本質的に「バーチャル」でありながら、成功のためには「リアル」以外のアプローチがほとんどない、というのが現状だ。
そこへ別のアプローチ、「バーチャルで完結する」という形式を打ち立てたのは、非常に大きな意味を持つと感じた。
オンラインということで、チートや遅延など、解決すべき問題も多い。それでもiRacingのような形式を洗練させていくことで、レースに限らずいろいろなスポーツや競技が、世界中の物理的な制約を越えて、健全なシーンを生み出す、という未来の可能性に思いを馳せると、胸が熱くなるものがある。
今後も、e-Sportsの大規模なイベントなどでは「リアル」の介入は不可欠だろう。でも、それ以外の小規模で日常的なゲームシーンにも、e-Sportsという属性を波及させることができるとしたら、それはこういう方式がひとつの解答になるのかもしれない。