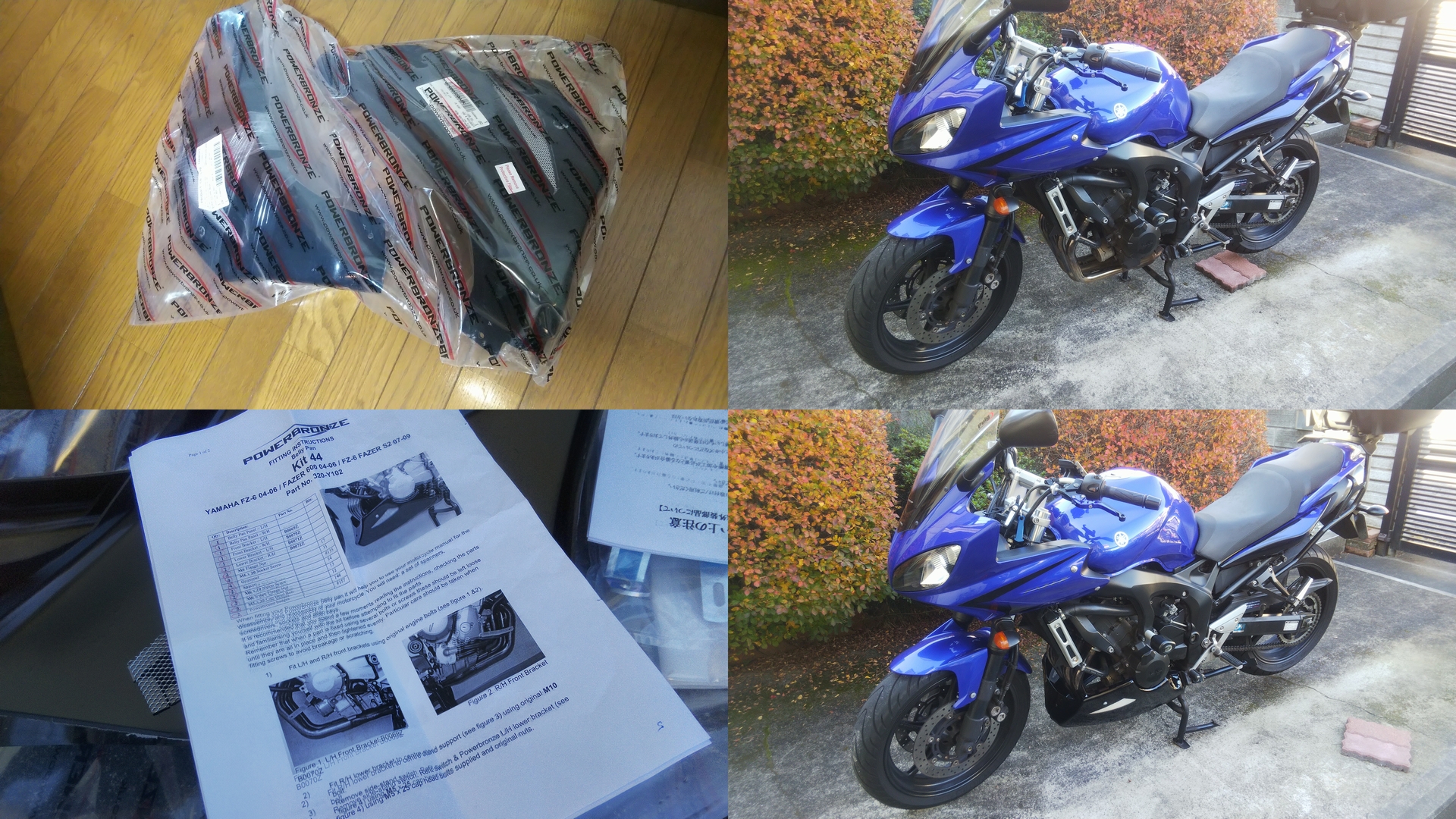というのも写真(右下ワイプ)のように、長年使い続けた冬グローブが、ついに破けてしまったからだ。
いや、よく使ったなコレ、この破れたグローブ。
いつ買ったのかも覚えてないくらい、冬はずーっとこのグローブだった。冬はバイクに乗る機会が少ないから、使用頻度が低くて、長持ちしてしまうんだろうな。この前のさらに先代の冬グローブについては、もはやまったく記憶がないから、下手すると15年以上前のゼルビス時代のものかもしれない。我ながら物持ちがいいというか、引き伸ばしすぎというか。
そんな長い付き合いとなった今までのグローブは、ゴールドウィンの冬グローブ。タグを見るとGSM6655と書いてある。ググってもヤフオクのログがでてくるくらいで、今となってはウェブ上にすらその記録がないような骨とう品だ。
昔はバイクギアにろくなデザインがなかった、という話は何度かしたかと思うんだけど、そんな中ではゴールドウィンのものは飾り気がなく地味で、無難なものが多かったので、一時期は好んで買っていたんだよなぁ、ということを思い出した。今でも使っている、これまた年代物のメッシュジャケットはゴールドウィンだし、先々代のメッシュグローブもゴールドウィンだった。
最近のゴールドウィンは、バイクギアメーカーとしてはなんだか存在感がないというか、高級志向に寄り過ぎて大衆向けではなくなってしまっているような、遠い存在になった気がするけど、元愛用者としてはもう少し身近なメーカーに戻ってきてほしいものだ。
で、新しく買ったのは、コミネのグローブだ。型番はGK-801。
コミネはもう本当に元気なメーカーというか、ゴールドウィンとはうってかわって、身近も身近な、大衆寄りのメーカーだ。コスパのいいバイクギアを探せば、必ず選択肢に入ってしまうような優良メーカー。今年は、メッシュグローブも買い替え、冬グローブも買い替えたわけだけど、どちらもコミネになってしまった。さらに冬ジャケットもコミネだし、もう私も立派なコミネマンだな。
新しいグローブの使用感は、実はまだ試走していないのでわからない。ゴールドウィンのグローブは、もうボロボロだったこともあって、だいぶ寒いものだったから、その辺が少しでも改善されていることを期待しているよ。